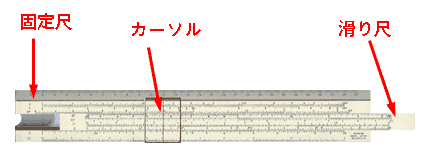計算尺超入門
|
| 計算尺は、特殊な目盛りの刻まれた定規状の物を操作して、掛け算・割り算・関数計算等を行う道具です。 計算尺の各部の呼び名は様々あるようですし、計算方法も一つではありません。メーカや製品によって構造等も異なりますが、「超入門」ということで、限定的な説明とさせて頂きます。 |
|
|
| 計算方法 計算尺の基本である、掛け算と割り算の計算方法を説明します。 位取りについて 掛け算・割り算に用いる計算尺の目盛りの範囲は、1~10です。 例えば、3×40を計算するとき、計算尺では3×4を計算します。 計算尺から読み取られる答えは(約)1.2になります。 (約)120の答えを得るには、計算をする人が自分で位取りを行う必要があります。 掛け算( a × b = c を計算する) ①カーソルを動かして、カーソル線をD目盛りのaに合わせます。 ②滑り尺を動かして、CI目盛りのbをカーソル線に合わせます。 ③C目盛りの基線(1または10)に合っているD目盛りを読んでcを得ます。 割り算( a ÷ b = c を計算する) ①カーソルを動かして、カーソル線をD目盛りのaに合わせます。 ②滑り尺を動かして、C目盛りのbをカーソル線に合わせます。 ③C目盛りの基線(1または10)に合っているD目盛りを読んでcを得ます。 (検索サイト等から直接このページにお見えになった方へ) このページは、私のページの、計算尺のページに関する説明です。
|